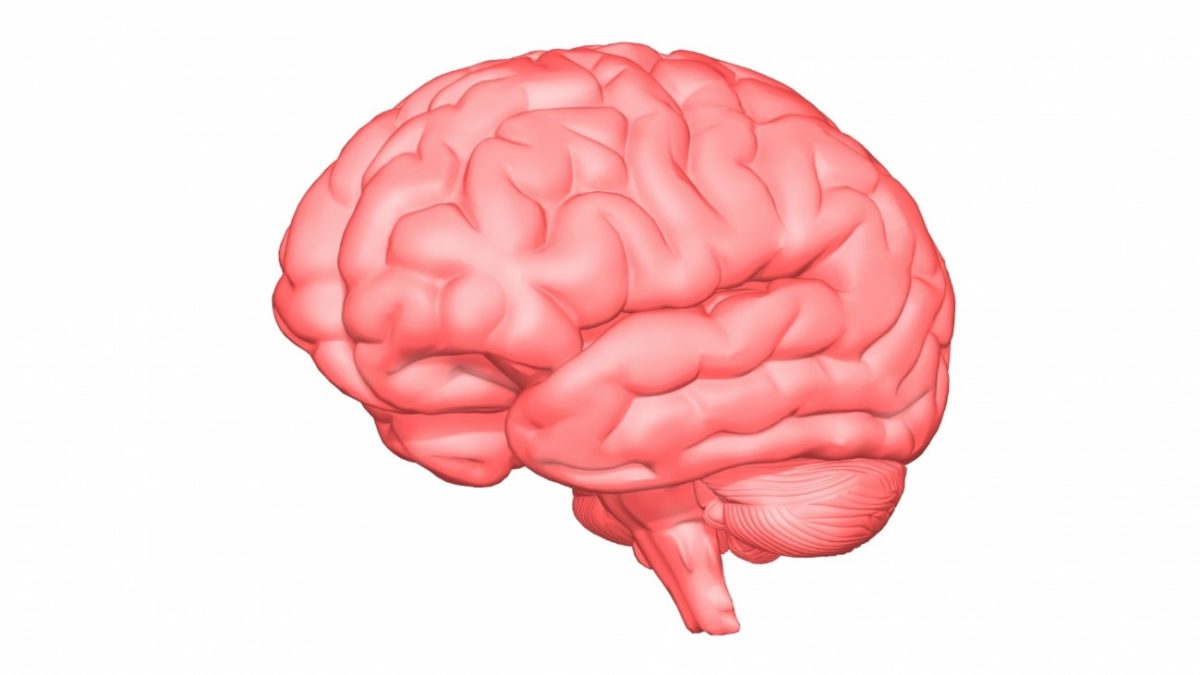家族が大脳皮質基底核変性症と診断されたけれど、聴いたことがない病気なのでどのように本人をサポートしたらよいかわからず困っている人はいませんか?
この記事では大脳皮質基底核変性症の原因や症状、介護のコツについて詳しく解説します。
大脳皮質基底核変性症とは?
大脳皮質基底核変性症とは筋肉の硬さ、運動の遅さ、歩行障がいなどのパーキンソン症状と手が思うように使えない、動作がぎこちないないなどの大脳皮質症状が同時に見られる病気で、日本では指定難病の7に指定されています。
40才以降に発病し、日本では10万人に3.5人程度しかいない珍しい病気ですが、過去の生活歴や病気で発病に関係するものはなく、遺伝性もありません。
参考:難病情報センター「大脳皮質基底核変性症(指定難病7)」
大脳皮質基底核変性症の原因
大脳皮質基底核変性症の患者さんの脳を調べると前頭葉と頭頂葉に強い萎縮があり、神経細胞の脱落やグリア細胞(構造の支持や栄養補給をして神経細胞をサポートする細胞)内に正常ではない構造が見られます。
しかしなぜこのような変化が起こるのかはわかっていないため、今の所発症する原因は明らかになっていません。
大脳皮質基底核変性症の症状
大脳皮質基底核変性症の主な症状は次の通りです。
| 症状 | 概要 |
| 失行 | ・物事のやり方や手順がわからなくなる ・動作がぎこちなくなる |
| 失語 | ・言葉が思うように出なくなる |
| 半側空間無視 | ・片方の空間にあるものを見落とす |
| 他人の手徴候 | ・自分の意思とは関係なく手が動く |
| 立体的な形の感覚障がい | ・目を閉じて物を触った時に何かわからない |
| 把握反射 | ・目につくものをつかもうとする |
| ジストニア | ・手足に勝手に持続的な力が入る ・左右どちらかに強く特に腕で現れやすい |
| 動作が遅く少なくなる | ・パーキンソン病に似た症状 |
| 振戦 | ・パーキンソン病と異なり早く不規則で衝動的にビクっと動く |
| ミオクローヌス | ・手足のぴくつき |
| 姿勢保持障がい | ・進行すると身体のバランスが悪くなり転倒しやすくなる |
| 構音障がい | ・進行すると呂律が回らなくなる |
| 嚥下障がい | ・食べ物を飲み込みにくくなる |
身体の右と左で症状に差があるのが特徴とされますが、左右差がない場合、認知症の症状が目立つ場合など症状が多岐に渡ることが最近わかってきました。
また病気の進行に伴い次のような合併症を引き起こす可能性があるため、予防方法とともにご紹介します。
| 合併症の種類 | 概要 | 予防方法 |
| 転倒による骨折 | ・廊下、トイレ、洗面所、風呂場など家の中で転んで骨折してしまう | ・手すりをつける ・屋外と屋内の段差をなくす ・リハビリをする |
| 誤嚥による肺炎 | ・飲み込む能力が低くなり誤嚥をしても食べ物を吐き出すことができず肺炎を引き起こす | ・現在の飲み込む能力を調べる ・大きさ、柔らかさ、とろみなどをつけて飲み込みやすい食事を作る ・口の中を清潔に保つ |
| 臥床に伴う褥瘡 | ・寝たきりになり褥瘡が発生する | ・入浴や清拭で清潔を保つ ・体位交換をする ・栄養管理をする |
合併症に不安を感じる人も多いかもしれませんが、予防ができるため今できることはないか本人の状態を見て考えてみるのがよいでしょう。
参考:難病情報センター「大脳皮質基底核変性症(指定難病7)」
参考:一般社団法人PSP・CBDのぞみの会「大脳皮質基底核変性症(CBD)診療とケアマニュアルVer.2」
大脳皮質基底核変性症の予後
大脳皮質基底核変性症は現在の医学では進行を止めることができず、発病から寝たきりになるまでの期間は5年~10年程度とされますが、個人差が大きいのが特徴的と言えるでしょう。
死因は誤嚥性肺炎もしくは寝たきりになることによる全身衰弱が多いため、全身管理の程度によって左右されます。
誤嚥性肺炎についてもっと詳しく知りたい方は、次の記事もごらんください。
大脳皮質基底核変性症の治療
大脳皮質基底核変性症を根本的に治す治療方法は今の所ありません。
しかし症状を緩和させる治療(対症療法)には次のような種類があります。
| 症状の種類 | 治療方法 |
| 動作が遅く少なくなる | ・塩酸トリヘキシフェニジルの内服 ・レボドパの内服 |
| 振戦・ミオクローヌス | ・クロナゼパムの内服 ・バルプロ酸の内服 |
| 身体のつっぱり | ・バクロフェンの内服 ・ボツリヌス毒素の注射 |
| ジストニア | ・塩酸トリヘキシフェニジルの内服 ・ボツリヌス毒素の注射 |
また、飲み込みが悪くなり食事が十分とれなくなった際は経管栄養を検討するのもよいのですが、医師と十分相談することが大切です。
大脳皮質基底核変性症のリハビリテーション
大脳皮質基底核変性症の患者さんが、日常生活動作(ADL)を維持するためにはリハビリテーションを行うのも大切です。
リハビリテーションには理学療法士(PT)による理学療法、作業療法士(OT)による作業療法、言語聴覚士(ST)による言語聴覚療法があります。
大脳皮質基底核変性症の患者さんに行う基本的なリハビリテーションは次の通りです。
| 項目 | 概要 |
| 身体のリハビリ | ・手足の運動(仰向けに寝てバンザイをするなど) ・足の屈伸運動 ・棒などを使って腕を上げる ・身体をねじる運動 ・うつぶせ寝 ・膝を伸ばして足を持ち上げる運動 ・仰向けに寝てお尻上げ ・手引き歩行 |
| 日常生活でのリハビリ | ・転倒に注意する ・本人が活動しやすい生活環境を整える |
| 声や飲み込みに関するリハビリ | ・声を出す練習 ・飲食の前に口を大きく開けたり舌を前後左右に動かしたりする練習 ・嚥下体操 |
どのリハビリテーションも専門家に相談の上、本人が楽しく続けられるよう配慮しましょう。
大脳皮質基底核変性症の介護
大脳皮質基底核変性症の患者さんに介護が必要となったら、どのようなことに気を付けて行うのがよいのでしょうか。
日常生活、事故防止、食事の3つの観点からご紹介します。
日常生活
物事のやり方や手順がわからなくなる失行、言葉が思うように出なくなる失語の症状は本人も動揺するため、慌てずゆっくり行動するよう声がけをしてみてください。
また片方の空間にあるものを見落とす半側空間無視の症状が起こると、片側にあるおかずが見えないため手をつけず、栄養バランスが偏る可能性があります。
見落とした方におかずがあることを知らせ、少しずつでも食べてもらうよう配慮することが大切です。
事故防止
大脳皮質基底核変性症の患者さんが生活する上で気を付けたいのが転倒なので、予防するための介護のポイントをご紹介します。
| 介護のポイント | 概要 |
| 排泄・入浴時に目を離さない | ・浴室とトイレは転倒しやすいため手すりなど安全対策をしておく ・狭く転倒しやすい空間なのでプライバシーに配慮しつつ見守りをする |
| トイレ誘導を行う | ・本人の排泄パターンに応じて声がけしトイレに行くよう促す |
| 声がけをする | ・廊下、トイレ、洗面所、風呂場など転倒しやすい場所に本人が行く際は声がけをして安全確認する |
| 周囲の物を整理していく | ・何かを落とした際拾おうとして転倒することがあるため必要なものを精査して整理・整頓を心がける |
| ケガをしにくいよう保護する | ・クッション素材のマットを敷くなどケガを最小限にとどめるための工夫を施す |
一般社団法人PSP・CBDのぞみの会のホームページには大脳皮質基底核変性症の患者さんの転倒防止に役立つ参考資料が掲載されているため、興味のある人は目を通してみてください。
参考:一般社団法人PSP・CBDのぞみの会「自宅で転ばないために」
食事
食べ物が飲み込みにくくなる嚥下障がいはむせる回数が増えたり、飲み込めずにいたりすることから始まります。
この時無理に食べさせようとすると誤嚥や窒息につながるため、食材を小さく切る、とろみをつける、やわらかく煮るなど本人が食べやすい形の食形態に変えていきましょう。
時間がかかってもできるだけ自分で食べられるよう配慮することが本人の自信にもつながります。
利用できる医療・介護制度
大脳皮質基底核変性症は指定難病のため、医療費助成制度を利用することができます。
医療費助成の申請から医療費受給者証交付までの流れは次の通りです。
- 必要書類を添えて都道府県・指定都市に申請
- 都道府県・指定都市による審査
- 都道府県・指定都市による医療費受給者証の交付(申請から交付までは3ヵ月程度、不認定の場合は不認定通知が送付される)
申請に必要な書類は次の9種類です。
- 特定医療費の支給認定申請書
- 診断書(臨床調査個人票)
- 住民票(申請者および申請者の世帯の構成員のうち申請者と同一の医療保険に加入している人が確認できるものに限る)
- 世帯の所得を確認できる書類(市町村民税非課税証明書など)
- 保険証の写し
- 人工呼吸器装着者であることを証明する書類
- 世帯内に申請者以外に特定医療費または小児慢性特定疾病医療費の受給者がいることを証明する書類
- 医療費について確認できる書類
- 同意書
6.7.8は必要に応じて提出が必要です。
医療費助成による自己負担上限額は世帯の所得によって異なるため、詳細は難病情報センターのホームページで確認してみましょう。
一方大脳皮質基底核変性症の患者で日常生活の支援が必要な場合、介護保険サービスを利用したり、身体障害者手帳を取得したりできます。
利用できる医療や介護の制度をうまく活用して、本人が生活しやすい環境を整えましょう。
参考:難病情報センター「指定難病患者の医療費助成制度のご案内」
参考:一般社団法人PSP・CBDのぞみの会「大脳皮質基底核変性症(CBD)診療とケアマニュアルVer.2」
宅配クック123では大脳皮質基底核変性症の方の食事での健康管理をサポートします
宅配クック123では大脳皮質基底核変性症の患者さんを食事面からサポートしたいと考えています。
宅配クック123では飲み込む力が弱くなった方向けに「ムースセット食」をご用意しています。
ムースセット食はムースのようなやわらかさが特徴の農林水産省が推奨するスマイルケア食の1つで、管理栄養士監修のもと、一食あたりおかず+おかゆ250gで378~412kcal、食塩相当量2.0g未満を目安に作られています。
大脳皮質基底核変性症の患者さんが食べやすいように配慮しながら、必要な栄養バランスがしっかりと維持できるようになっているのです。
大脳皮質基底核変性症の患者さんに、できるだけ長い期間食べる喜びを味わってほしい。
宅配クック123はそんな気持ちでお弁当をお届けしています。

まとめ
大脳皮質基底核変性症とは筋肉の硬さ、運動の遅さ、歩行障がいなどのパーキンソン症状と手が思うように使えない、動作がぎこちないないなどの大脳皮質症状が同時に見られる病気で、日本では指定難病となっています。
この記事も参考にして、ぜひ大脳皮質基底核変性症への理解を深めてみてください。